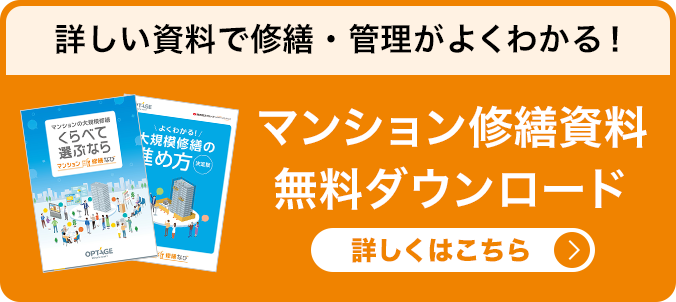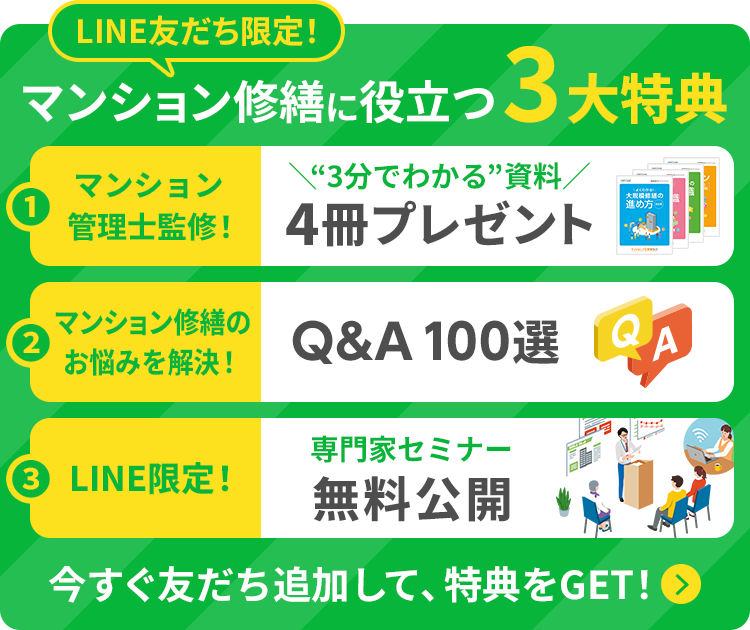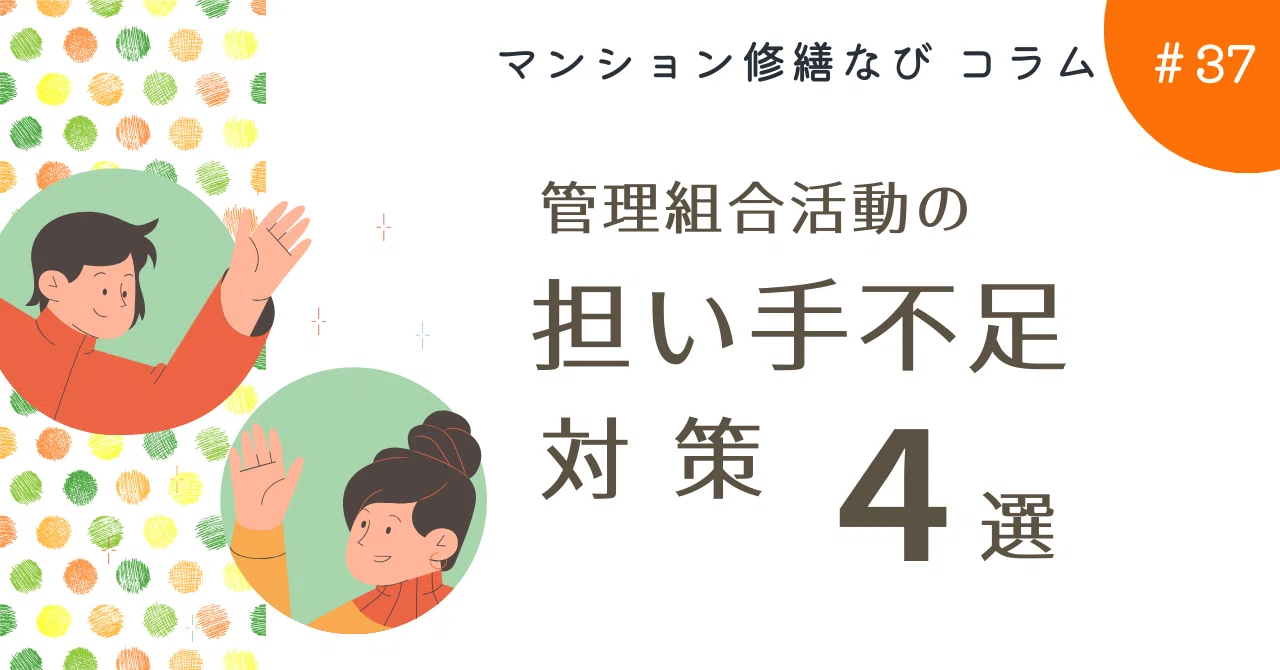
2025.5.8
管理組合活動の担い手不足、対策4選!
この記事では、管理組合活動の担い手不足の原因とその対策について詳しくご説明します。
マンション修繕にまつわるさまざまな資料を無料配布中!
疑問の解消や情報共有など、幅広くご活用ください。
1.担い手不足に陥る要因
組合の担い手不足の主要因子は、組合員の高齢化です。能力的・体力的に対応可能な組合員が減少すると、理事の職務を一部の組合員が一手に引き受けざるを得ない状況となります。
また、管理組合が機能不全に陥っている場合も、担い手不足を招きます。例えば、一部の理事が管理組合に長年従事していたり、理事会が管理会社の言いなりで費用の支出を認めるだけの場になっていたりすると、その他大勢の組合員は組合活動の意義を見出せず、参加を敬遠・放棄することになります。
こうして、組合運営に対する無関心が全体に広がると、担い手不足に拍車が掛かります。
<担い手不足の要因>
・区分所有者の高齢化
・組合運営の形骸化
・組合運営への無関心

2.担い手不足対策4選
では、どのようにすれば、組合運営の担い手不足を軽減できるでしょうか。具体的にご紹介します。
①理事就任資格範囲の拡大
多くの組合では、「理事は組合員の中から選出する」と規約で定められています。「組合員」とは、管理組合に区分所有者として登録されている人のことで、区分所有者の配偶者や子・親などは例えマンションに同居していたとしても、組合員ではないため、理事に就任することは出来ません。
また、「理事はマンション内に居住する組合員」から選出すると規定されている組合では、マンションに居住していない組合員は理事に就任できない場合もあります。
このように、理事に就任できる人の範囲は、狭く限定されているのが一般的です。担い手不足解決の一策としては、規約を改正し、この範囲の拡大を検討してみましょう。
例えば、組合員の同居親族(配偶者・親・子など)の理事就任を認めてもよいですし、マンションに居住していない組合員の理事就任も有り得るかもしれません。マンションに同居していない子や親にまで資格範囲を拡大することも一考の価値があります。WEB理事会などを導入し、参加を容易にすることも併せて検討しましょう。
② 外部専門家の活用
組合運営の効率を上げれば、理事の職務自体が軽減します。この点では、外部専門家の活用は有効です。例えば、設計事務所の建築士やマンション管理士などを採用すれば、組合のハード面、ソフト面双方の専門的知識や手法が活用できます。組合の問題に効率よく対応できるようになるでしょう。
●マンション管理士については、コラム「マンション管理士のお仕事」をご参照ください
③役割の明確化と分担
理事長の職務は管理規約に明記されていても、他の役員や理事の職務は明確となっていない組合があります。結果として、理事長一人に職務が集中することになり、理事長職が敬遠されるのです。実際に、誰が理事長に就任するかの議論に何時間も費やす現場に、私も複数回立ち会ったことがあります。理事に就任するのは仕方ないが、理事長だけは嫌だというわけです。
理事長一人への職務集中を避けるため、役割分担を明確にし、それぞれの理事が一定の役割を担う仕組みを導入し、理事長及びその他理事就任のハードルを下げるのです。
●理事長の役割についてはコラム「理事長になったら」をご参照ください
●監事の役割についてはコラム「よくわかる!マンション管理組合監事の役割」をご参照ください
●会計の役割についてはコラム「責任重大?!会計担当理事は何をする?」をご参照ください
④勉強会の開催
新しく理事が就任した際には、組合運営の重要性やその方法、
理事の職務について学ぶ機会を設けるべきでしょう。
また、会議の形骸化を防ぐため、理事全員の参加を促すような決まりを設けましょう。ある委員会では、「全員が意見を述べる」という基本方針の下、非常に活発な議論がおこなわれており、私も驚かされたことがあります。組合運営への参加を促すちょっとした工夫が、大いに役立つこともあるようです。
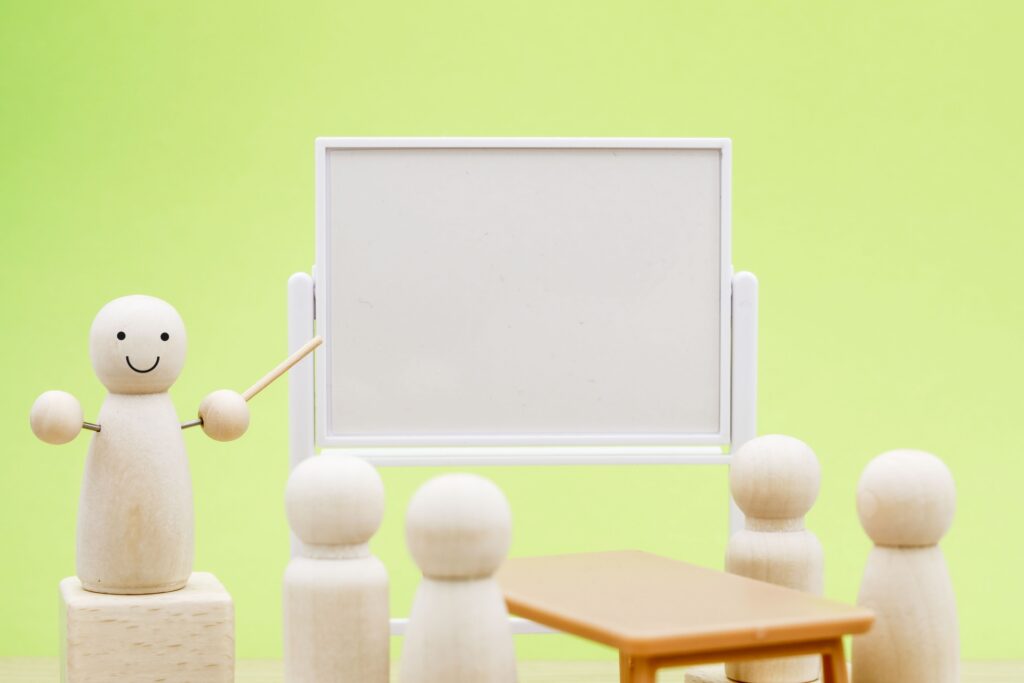
3.外部専門家による理事長就任は解決策になるか?
ここで「外部専門家による理事長就任(外部管理者方式)は解決策になるか?」について考えてみます。
管理組合の「外部管理者方式」とは、マンション管理運営に関して、管理組合員以外の第三者が組合の理事長(管理者)に就任しその職務を代行するものです。管理規約に定めれば、第三者が理事長に就任し、理事会を設けずに管理組合運営を行うことも制度上可能です。この場合、組合員が管理運営をコントロールすることは殆ど不可能となるでしょう。
特に、管理会社は、管理を委託されており厳密には「外部」と言えない上、営利を目的に経済活動を行う組織です。担い手不足のために、安易な「管理会社による理事長就任(管理業者管理者方式)」導入は、お勧めできません。国も、この方式に規制を設けようと、法律の改正が予定されています。
ほかにも、管理会社以外の事業者が理事長に就任する「外部管理者方式」が現れており、こちらは法規制の範囲外となっています。この方式の採用は、より慎重にならねばなりません。
4.まとめ
マンションの高経年化と組合員の高齢化が進むのですから、管理組合運営に人手が足りない組合は、今後一層増えていきます。放置して深刻化する前に議論を始め、早めに対策を講じる必要があります。

マンション修繕・管理にお悩みなら
専門家による無料セミナーで解決のヒントを見つけましょう
いかがでしたか?
担い手不足も、小さな工夫の積み重ねで、解決とまではいかずとも悪化を防ぐことは出来るはずです。専門家を活用したり、勉強会を開いたり、組合運営のセミナーに参加したり、外部の力を活用しながら組合自ら課題解決に取り組んでください。
マンション修繕なび では、専門家とのマッチングサービスで管理組合の課題解決をお手伝いしています。修繕に関する勉強会の開催や、組合運営方法の個別相談など様々な場面で活用いただいています。管理組合のためのお役立ち動画やコラム、メルマガ、無料セミナーをご用意しています。ぜひご活用ください。

マンション管理
コンサルタント事務所
代表 大野 かな子
(マンション管理士)
国内メーカー勤務後、大手管理会社でマンション担当者として勤務。
これからのマンション管理には、“管理会社管理”や“自主管理”とは異なる第三の選択肢が必要と考え、マンション管理組合に対する管理ノウハウを提供し実務を支援する「ちいさな管理」を立ち上げる。
(株)ビル新聞社が発行する「ビル新聞」へマンション管理コラムを連載中。
マンション管理の専門家として、マンション管理に関する市場調査レポートを発表している。
ちいさな管理ホームページ:
https://s-kanri.com
おすすめのコラム
-
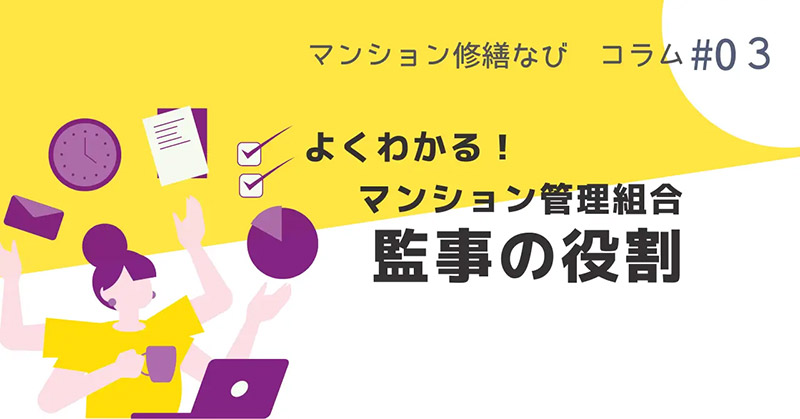
よくわかる!マンション管理組合監事の役割
2024.3.15
-
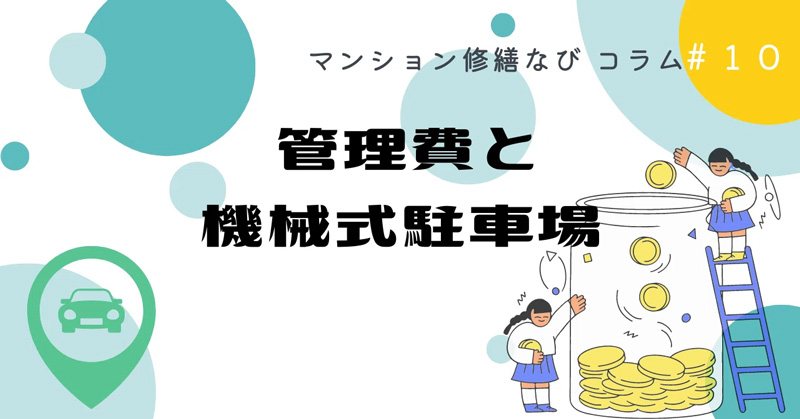
管理費と機械式駐車場 ~なぜ管理組合会計から修繕費を出すのか問題~
2024.7.5
-
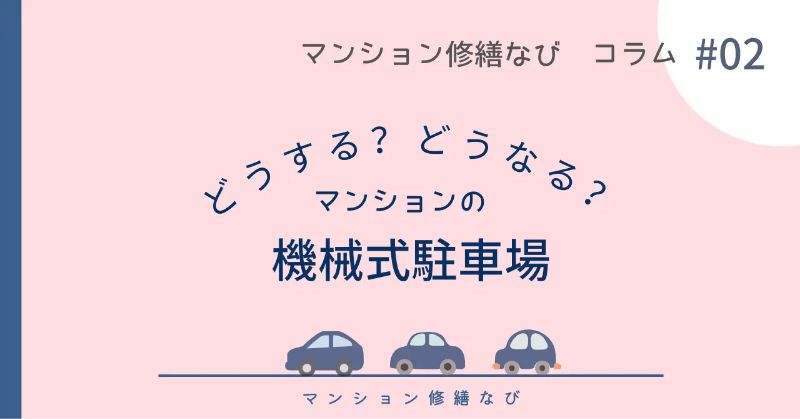
どうする?どうなる? マンションの機械式駐車場
2024.3.15